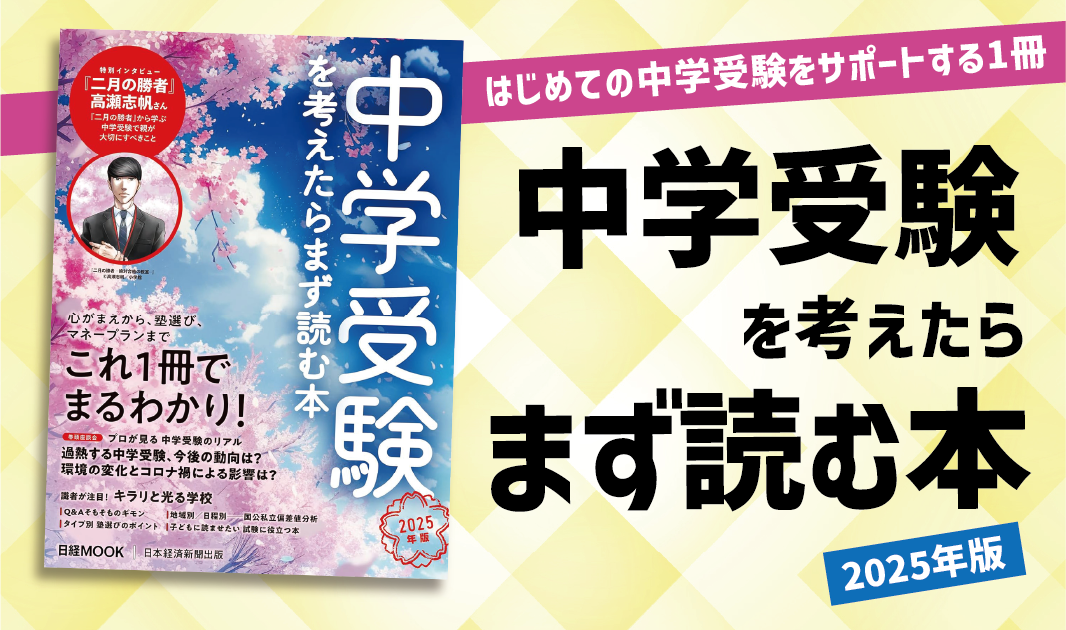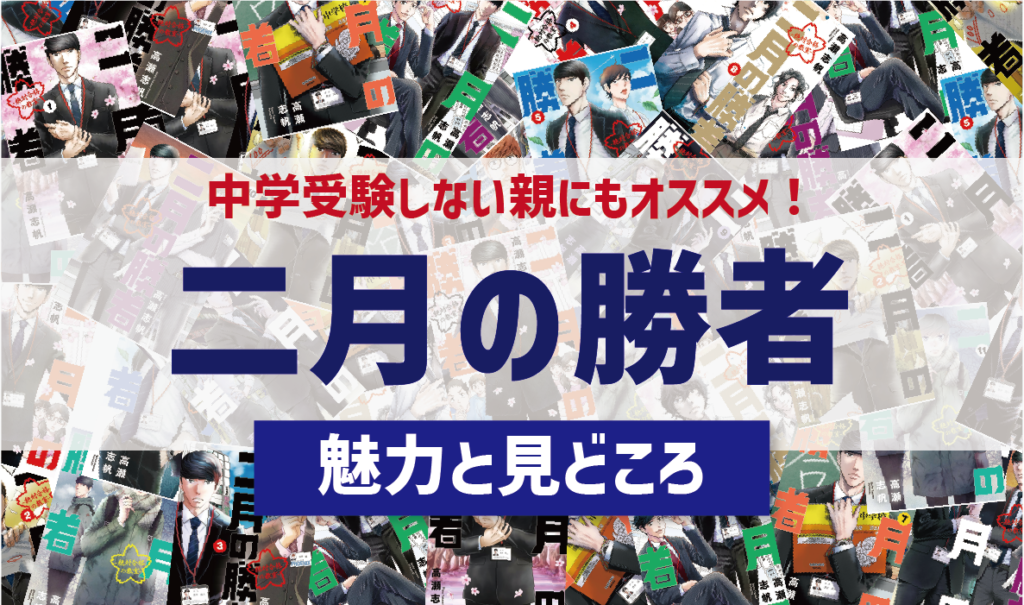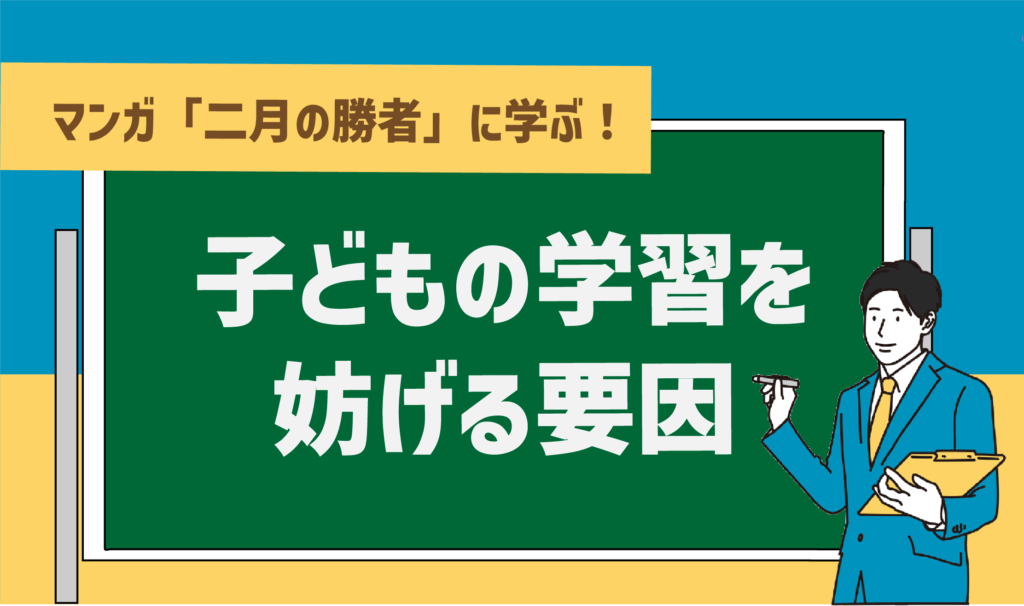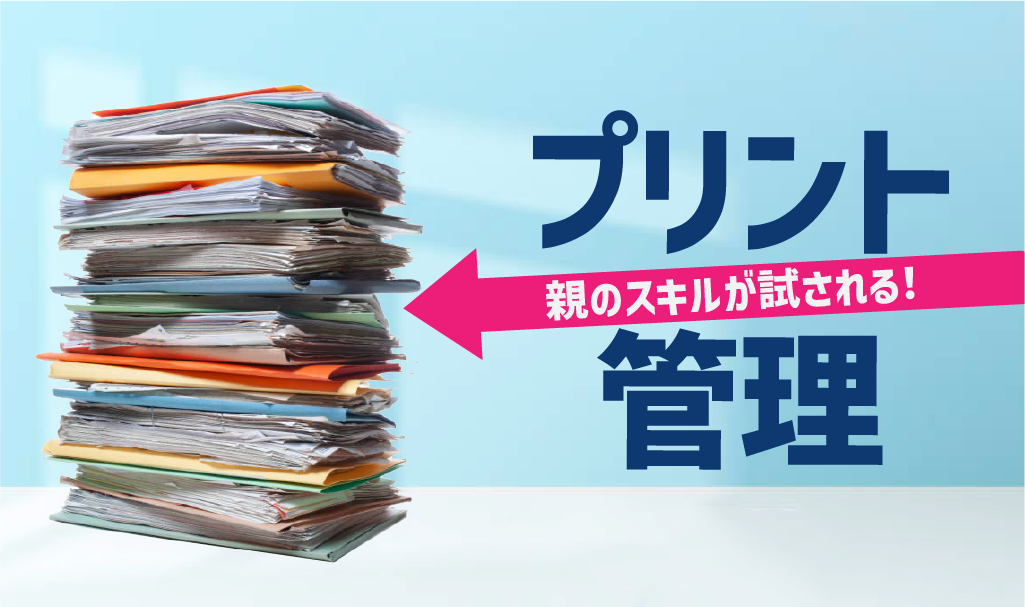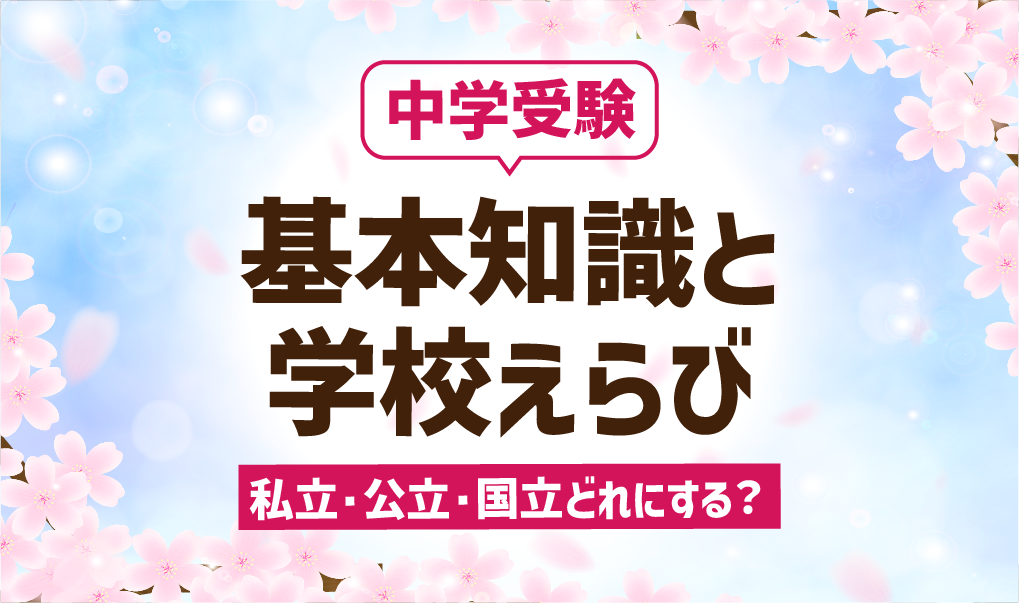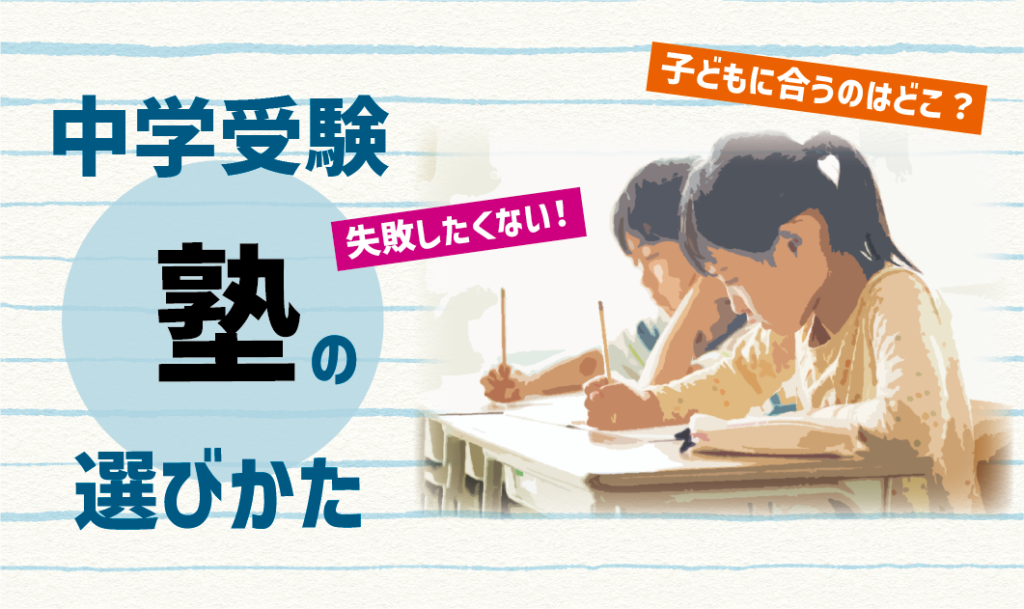
みなさん、こんにちは!スタッキーです。
少子化が進む一方で、首都圏や関西圏では、中学受験をする人数が増えてきています。
2024年は、4.7人に1人が受験しており中学受験は特別なものではなくなってきています。
中学受験を考えると、はじめに考えるのがどこの塾のお世話になるのがいいか、ですよね。
最近では、中学受験を見据えて低学年から塾に通わせたいと考える家庭もあるようです。
今回は、塾の選び方や気をつけるポイントについてご紹介します。
この記事は次のような人におすすめ!
・中学受験を検討しはじめた
・受験対策をはやめに開始したい
・塾選びで失敗したくない
・塾を選びのポイントをしりたい
今回は、中学受験「塾」を選ぶときのポイントをご紹介したいと思います。
塾選びで失敗したくない、早めに受験対策をしたい方におすすめの内容です。
それではどうぞ!
※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。
塾選びが重要なワケ

塾は、小学校とは異なり、学力向上や受験に特化した指導が受けられます。
中学受験で塾選びが重要なのは、塾は志望校への合否を左右する大きな要素だからです。
子どもの性格や勉強量に合った塾で学べば、成績が上がり志望校合格の可能性が高まります。
反対に、合わない塾は勉強嫌いや親子関係の悪化、体調不良を引き起こすこともあります。
中学受験塾の宿題量は多く、子どもがこなせる範囲を超えると苦痛やストレスの原因に。
子どもとの関係を大切にし、勉強量や授業レベルが適切な塾を選ぶことが必要です。
塾選びは、子どもの成長や中学受験の成功に直結する重要なステップといえます。

塾選びの進め方
塾の情報収集から入塾するまで
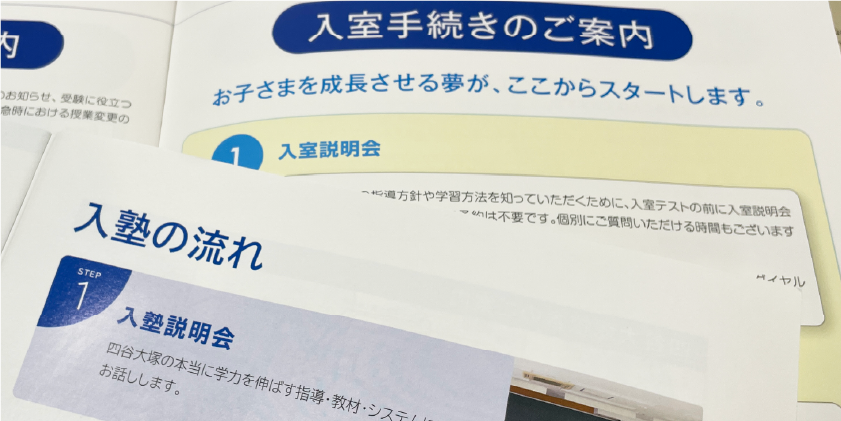
はじめに押さえておきたいのは塾の新学期は2月からということを覚えておきましょう。
なので、実際に塾に申し込みするタイミングは年末〜1月ごろになります。
1月くらいに説明会の開催や生徒募集のための体験授業などを行う塾が多いです。
Webでは塾の概要を把握できますが、費用やカリキュラムなど詳細は不明なことが多いです。
メールでも資料請求もできますが、そこは足を運んで塾にもらいに行くことをおすすめします。
入塾までは、塾に連絡→見学や体験授業→入塾テスト→入塾が一般的な流れです。
一部の塾では、兄弟がすでに通っていた場合には入塾しやすいなどの特典もあるようです。
実際に塾を子供と一緒に見にいき、良さそうなら体験授業に参加してみるといいでしょう。

体験授業を受けてみよう

事前に塾に連絡をすれば、ほとんどの塾が教室見学やカリキュラムの説明をしてくれます。
体験授業に参加できる塾も多く、受けてみることをおおすすめしますが注意点があります。
体験授業では、人気やベテラン講師の授業に参加するケースが多いです。
なので、体験授業が終わると子どもは楽しかった!という感想を言うことがあります。
しかし、担当した講師の授業やクラスに必ずしも所属できるわけではないので注意です。
体験授業では子どもだけでなく親も授業の様子を見てみるといいでしょう。
どんな子たちが学んでいるのか、授業の雰囲気など親の目で見ておくことは大事です。
また、塾から説明を受けるときには、通知表やテスト結果持っていくと良いでしょう。
塾側から子どもの今の状況に合った意見やアドバイスをもらえる可能性大です。
入塾テストに合格しないといけない
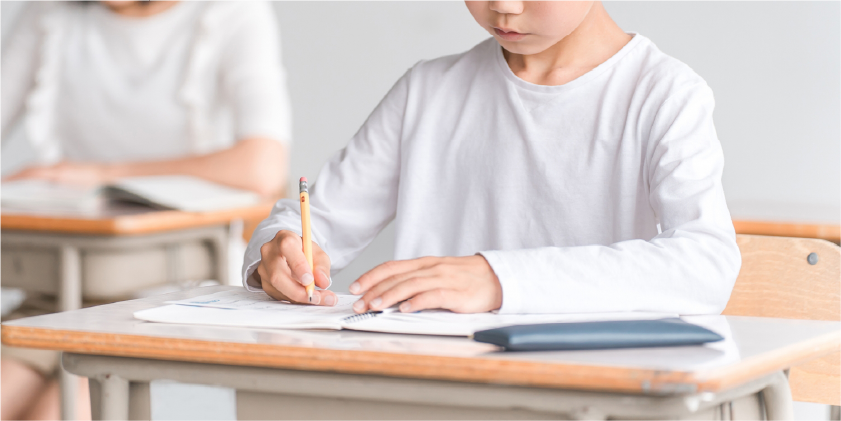
体験授業を受けたのならその流れで入塾のためのテストを受けることになるでしょう。
無料で受けれますし、塾が設定している基準を満たせば入塾することができます。
塾のテストは、小学校のテストよりも難しいので点数は低くなることが一般的です。
テストは何度も受けることができますので、基準を満たせなくても何度も挑戦できます。
また、全国統一小学生テストなどの公開テストの点数次第で入塾できる塾もあります。
ただし、難関校を目指す場合、4年生以降からの入塾は、ハードルが高い場合があります。
というのは、4年生から受験が本格化するため入塾する人数が一気に増えてきます。
そのため、上位クラスを狙うには、事前に対策してテストで高い点数を取る必要があります。
最近では、入塾できないリスクを回避するため、新3年生から塾に通わせる家庭もあります。
塾選びのポイント
塾選びのポイント8つ

ひとことで塾といっても、塾のタイプはいろいろあります。
例えば、サピックスは、勉強が得意でトップレベルを目指していきたい子に向いています。
四谷大塚は、テキストも改定され難関高向けへシフトしてきている傾向にあります。
また、進学くらぶなどのデジタルコンテンツが充実している点も特徴です。
早稲アカや浜学園は、講師の合格をつかみ取るための熱血指導が人気があります。
しかし、反復型の学習のため宿題量が多く、反復処理が早い子でないと大変のようです。
一方、大手塾だけでなく、個人指導やオンラインなどの学習サポートも増えています。
個別指導のトライやTOMASなどは手厚い指導が受けられ、学習理解が深まりやすいです。
ただし、費用が高いことや競争意識が育ちにくい、受験情報が少ないなどのデメリットも。
オンラインは、自宅で学習できますがモチベーション維持が難しいと言う意見もあります。
このように、塾にはさまざまなタイプや受講形態がありメリットデメリットがあります。
今回は、塾選びの際にチェックしておくべきポイントをまとめてみました。
(週刊ダイヤモンド、東洋経済などの情報誌を参考にまとめています。)
以下のポイントを評価してみて、子どもや家庭にとってベストな塾を探してみてください。
| 1 | 通いやすさ | 高学年になるほど帰りが遅くなるので30分前後で通える距離が良い。距離が長くなると睡眠時間や家庭学習時間が短くなる。通塾経路が安全かの確認も必要。 |
| 2 | 塾の規模 | 大手は運営に安心感があるが、中小規模やオンライン個別などは倒産などの危険もあるため運営実績や生徒数を確認しておく。 |
| 3 | 合格実績 | 塾全体の合格実績ではなく、子どもが通う校舎の合格実績を見ること。その校舎の実績、子どもの志望校への実績の2つの観点で見ることが大事。 |
| 4 | カリキュラムの進度 | 難関校を目指す塾では授業進度が速いので、クラスごとのカリキュラムの進度や1年間の学習量を見て子どもがついていけるかを確認する。 |
| 5 | 面倒見の良さ | 宿題のチェックや質問がしやすいか、苦手な部分をサポートしてくれるかなど子どもの学習をどこまで面倒を見てくれるのか聞いておく。 |
| 6 | 通塾頻度 | 学年やクラスによって週の通塾回数が異なるが、少なすぎると家庭学習の量がより重要になってくるため、週に必要な学習時間のうち、塾でどのくらい学習できるのかは調べたい。 |
| 7 | 講師の質 | 子どもの反応に合わせて授業しているかや質問に答えているかなど体験授業などで講師を見ておくとよい。(クラス変動が多い塾は講師も頻繁に変わるため) |
| 8 | 生徒のレベル | 通塾生はどんな子どもたちなのか、どのくらいの学力の生徒が多いのか(ボリュームゾーンの確認)聞いてみる。競争意識がある、アットホームなど授業の様子も見学しておく。 |
中学受験をしようかなと思った時に悩むのが塾選びでではないでしょうか?1つ1つ塾を調べていくのは大変ですよね。今回は、首都圏で有名塾な4大塾を徹底比較します!サピックス、四谷大塚、早稲田アカデミー、日能研の授業料、クラス分けなど特徴について紹介します。塾選びでお悩みの方の参考になれば幸いです。
塾選びを失敗しないために

塾選びのポイントを紹介しましたが、気をつけておきたい点もあります。
まずは、合格実績だけで塾を選んでしまうことはやめておきましょう。
塾の合格実績は、あくまで一部の生徒の結果で全ての生徒の実績ではありません。
塾によっては、合格実績を「見栄え良く」見せるための工夫がされている場合があります。
また、Webなどの口コミやレビュー、SNSでの評判などの情報にも気をつけたいです。
投稿者の個人的な感想や経験に基づいており、部分的な側面のみからの情報になります。
自分と投稿者との家庭環境も違います。一部の体験談だけで判断しないようにしましょう。
良い口コミが自分にとっての良さではない場合もあるので鵜呑みにしないことが重要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、中学受験「塾」の選びかたをご紹介しました。
中学受験の塾選びは、志望校への合格を左右する重要なイベントです。
選び方のポイントを参考に親子で話し合いながら、最適な塾を選んでくださいね。
- 子どもと一緒に塾に見学&体験授業に参加してみよう
- 中学受験をするなら低学年から入塾させるのもアリ
- 塾を選ぶときは8つのポイントをチェックしてみよう
- 合格実績や口コミだけで塾の良し悪しを決めるのは危険
中学受験において、塾は受験生の強い味方であり、頼りになる存在です。
子どもが最後まで意欲を持って学習し続けられる塾を探してみてください!
今後も中学受験に役立つ情報や教材を紹介していきたいと思います。
ご期待ください!
中学受験するかどうかを考え始めたらまず情報収集から始めたいですよね。今回は、はじめての中学受験をサポートしてくれる1冊「中学受験を考えたらまず読む本 2025年版」を紹介します。中学受験の全体像を知りたい、中学受験の疑問や不安を解消したい方におすすめです!